相続税がでるかでないか位の財産の人が相続で注意すべきこと
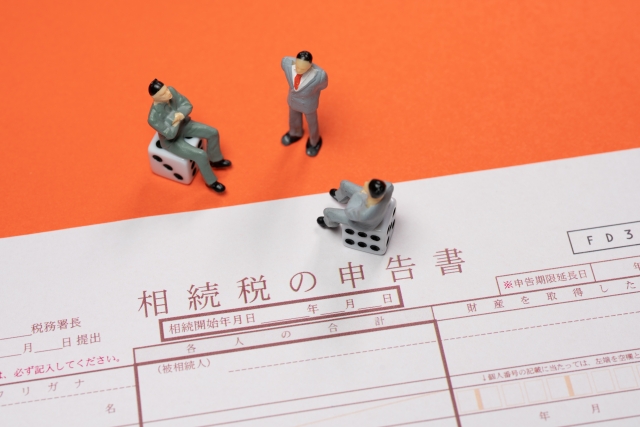
父が亡くなったと相談に来られたお客様。父の財産は、相続税の基礎控除額に近い額でした。このような場合に留意すべきことがいくつかあります。今回はそれら留意点を考慮し、無事に相続手続きが完了した事例をご紹介します。
まずは財産の確認から
父が亡くなり相談に来られたのは相続人である長男と母でした。
まずは財産の確認を行いました。
不動産は自宅と借家2軒を所有されていました。固定資産税評価額から、財産額が概算でどれくらいになるか確認しました。預貯金と合わせると相続税の基礎控除額に近い額になりそうでした。
そのため、より精緻に財産評価を行い、相続税が発生するかどうかを確認することにしました。
現地確認を行い不動産の評価をしました。接道の状況や土地の形状など確認したところ、土地の評価減になる要素がありました。
計算した結果、財産額は相続税の基礎控除額を下回る結果となりました。
この場合相続税は発生しないため申告は必要ありません。しかし後に、何か他に財産があることが判明し基礎控除額を超えてしまう恐れがあるのなら、相続税が発生しなくても申告しておくことはできます。申告しておけば「無申告」の状態を避けることができます。
仮に「無申告」の状態でその後何か財産が出てきて申告することになった場合には、申告期限は過ぎているので本来の相続税以外に「無申告加算税」を別途納税する必要が出てきてしまいますので注意が必要です。
今回は基礎控除額を数百万円下回っており、これ以上財産は無いということ確認取れましたので申告はしないことになりました。
まずは財産の確認を行いました。
不動産は自宅と借家2軒を所有されていました。固定資産税評価額から、財産額が概算でどれくらいになるか確認しました。預貯金と合わせると相続税の基礎控除額に近い額になりそうでした。
そのため、より精緻に財産評価を行い、相続税が発生するかどうかを確認することにしました。
現地確認を行い不動産の評価をしました。接道の状況や土地の形状など確認したところ、土地の評価減になる要素がありました。
計算した結果、財産額は相続税の基礎控除額を下回る結果となりました。
この場合相続税は発生しないため申告は必要ありません。しかし後に、何か他に財産があることが判明し基礎控除額を超えてしまう恐れがあるのなら、相続税が発生しなくても申告しておくことはできます。申告しておけば「無申告」の状態を避けることができます。
仮に「無申告」の状態でその後何か財産が出てきて申告することになった場合には、申告期限は過ぎているので本来の相続税以外に「無申告加算税」を別途納税する必要が出てきてしまいますので注意が必要です。
今回は基礎控除額を数百万円下回っており、これ以上財産は無いということ確認取れましたので申告はしないことになりました。
二次相続や所得税などを考えた遺産分割
続いて遺産分割協議に移りました。
長男からは全ての財産を母が相続することでお願いしたいと話がありました。母もすべて自分が相続することで良いとのことでした。
全て母が相続した場合は、父の財産がそのまま母の所有になります。母固有の財産がどれくらいあるか確認したところ、預貯金があるようです。
母に相続が発生した場合(二次相続)、相続人は長男1人で相続税の基礎控除額は3,600万円になります。父の財産と母固有の財産を合わせると基礎控除額を超えそうです。
今回父の相続税は発生しないので、どのように財産を相続しても納税はありません。そうであるならば、長男が全財産を相続しておけば、母の相続の際(二次相続)にも相続税は発生しないことになります。
このような一般的な内容をお伝えした後、お客様の状況に合わせたお話をしました。
自宅と借家2軒の土地は長男が相続し、借家2軒の家屋のみ母が相続するという内容です。
借家の家賃収入は家屋の所有者の不動産所得になります。母が相続すれば母の所得になります。長男が相続するのであれば長男の所得になります。長男は会社員で給与所得があります。そのため、給与所得と不動産所得を合算すると、所得税の税率が高くなります。母は年金以外の所得はありませんので、長男が相続するより税率は低くなります。所得税の観点からは母が相続するほうが良さそうです。
この場合、注意する点もあります。今まで母は父の扶養親族として扶養控除の対象でした。今は長男と生計を一にしているので、年金以外の所得が無ければ今後は長男の扶養親族になります。しかし不動産所得があると扶養親族から外れてしまいます。また、所得があると後期高齢者医療保険や介護保険料も高くなり、医療費の負担も2~3割負担になるケースもあるかもしれません。
今回全て母に相続したい意向でしたが、それは母には母の生活資金を確保してあげたいという長男の配慮からでした。その意向にも合致します。
税務面から、土地は相続を考慮して長男、家屋は所得税を考慮して母、と説明したところ、社会保険などの点も理解していただいたうえで借家2軒の家屋のみを母が相続することに決定しました。
長男からは全ての財産を母が相続することでお願いしたいと話がありました。母もすべて自分が相続することで良いとのことでした。
全て母が相続した場合は、父の財産がそのまま母の所有になります。母固有の財産がどれくらいあるか確認したところ、預貯金があるようです。
母に相続が発生した場合(二次相続)、相続人は長男1人で相続税の基礎控除額は3,600万円になります。父の財産と母固有の財産を合わせると基礎控除額を超えそうです。
今回父の相続税は発生しないので、どのように財産を相続しても納税はありません。そうであるならば、長男が全財産を相続しておけば、母の相続の際(二次相続)にも相続税は発生しないことになります。
このような一般的な内容をお伝えした後、お客様の状況に合わせたお話をしました。
自宅と借家2軒の土地は長男が相続し、借家2軒の家屋のみ母が相続するという内容です。
借家の家賃収入は家屋の所有者の不動産所得になります。母が相続すれば母の所得になります。長男が相続するのであれば長男の所得になります。長男は会社員で給与所得があります。そのため、給与所得と不動産所得を合算すると、所得税の税率が高くなります。母は年金以外の所得はありませんので、長男が相続するより税率は低くなります。所得税の観点からは母が相続するほうが良さそうです。
この場合、注意する点もあります。今まで母は父の扶養親族として扶養控除の対象でした。今は長男と生計を一にしているので、年金以外の所得が無ければ今後は長男の扶養親族になります。しかし不動産所得があると扶養親族から外れてしまいます。また、所得があると後期高齢者医療保険や介護保険料も高くなり、医療費の負担も2~3割負担になるケースもあるかもしれません。
今回全て母に相続したい意向でしたが、それは母には母の生活資金を確保してあげたいという長男の配慮からでした。その意向にも合致します。
税務面から、土地は相続を考慮して長男、家屋は所得税を考慮して母、と説明したところ、社会保険などの点も理解していただいたうえで借家2軒の家屋のみを母が相続することに決定しました。
土地の評価について考察
借家の土地は長男が相続しますが、母がその土地を借家のために利用します。特に地代のやり取りをしなくても問題はありません。なぜ今回このようにしたのか。
土地の評価方法についても以下のように検討をしました。
一般的に土地と建物の所有者が同一で誰かに賃貸している場合、相続税を計算する際の評価は「貸家建付地」となり、土地の評価が下がります。今回の父の相続は「貸家建付地」で評価しました。
母の相続の際、土地は無く家屋だけです。家屋と母の預貯金のみですと相続税の基礎控除額の範囲におさまります。
仮に長男の相続が母より先に起こってしまった場合には、土地の評価が「貸家建付地」でなく「自用地」評価となり評価減ができなくなります。長男が土地のみを相続するリスクはここにあります。
しかし、一般的には長男の相続の順番は母の相続の後で、まだまだです。
母の相続の後、家屋を長男が相続すれば「貸家建付地」での評価になります。
相続の順番、財産額の状況を考えても、土地は長男、家屋は母が相続することで問題ないと判断しました。
土地の評価方法についても以下のように検討をしました。
一般的に土地と建物の所有者が同一で誰かに賃貸している場合、相続税を計算する際の評価は「貸家建付地」となり、土地の評価が下がります。今回の父の相続は「貸家建付地」で評価しました。
母の相続の際、土地は無く家屋だけです。家屋と母の預貯金のみですと相続税の基礎控除額の範囲におさまります。
仮に長男の相続が母より先に起こってしまった場合には、土地の評価が「貸家建付地」でなく「自用地」評価となり評価減ができなくなります。長男が土地のみを相続するリスクはここにあります。
しかし、一般的には長男の相続の順番は母の相続の後で、まだまだです。
母の相続の後、家屋を長男が相続すれば「貸家建付地」での評価になります。
相続の順番、財産額の状況を考えても、土地は長男、家屋は母が相続することで問題ないと判断しました。
まとめ
親が二人いる場合、最初の相続では相続税が出なくても、その相続の仕方によっては二次相続時に相続税が出てしまうことがあります。
子からみると、両親のどちらかに相続が発生した場合、そのままもう片方の親が相続することで良いと考える人は多いと思います。財産額がそんなに無いよ、とおっしゃる方もいますが、父、母二人の財産が合わさると、相続税の基礎控除額位になるケースは意外とあります。
そのため、相続税が発生しないからといって簡単に相続の仕方を決めてしまうのではなく、両親の財産はどれほどかを必ず一度確認してもらうことを推奨しています。
また今回のように不動産所得がある場合は、誰が不動産を引き継ぐのか、所得税は誰が納めるのか、後悔することがないようにそれぞれの立場から考える必要があります。
木村美都子税理士事務所では、「無料相続シミュレーション」を一緒に行っております。今回のようなケースも含め、様々なパターンで検討することができます。相続税がどのくらいになるのか不安、相続税はかからなそうだけどそのまま遺産分割をしていいのか不安、相続に対する漠然とした不安等、色々あると思います。不安なこと、わからないことがある方はどうぞ気軽にご相談ください。
子からみると、両親のどちらかに相続が発生した場合、そのままもう片方の親が相続することで良いと考える人は多いと思います。財産額がそんなに無いよ、とおっしゃる方もいますが、父、母二人の財産が合わさると、相続税の基礎控除額位になるケースは意外とあります。
そのため、相続税が発生しないからといって簡単に相続の仕方を決めてしまうのではなく、両親の財産はどれほどかを必ず一度確認してもらうことを推奨しています。
また今回のように不動産所得がある場合は、誰が不動産を引き継ぐのか、所得税は誰が納めるのか、後悔することがないようにそれぞれの立場から考える必要があります。
木村美都子税理士事務所では、「無料相続シミュレーション」を一緒に行っております。今回のようなケースも含め、様々なパターンで検討することができます。相続税がどのくらいになるのか不安、相続税はかからなそうだけどそのまま遺産分割をしていいのか不安、相続に対する漠然とした不安等、色々あると思います。不安なこと、わからないことがある方はどうぞ気軽にご相談ください。