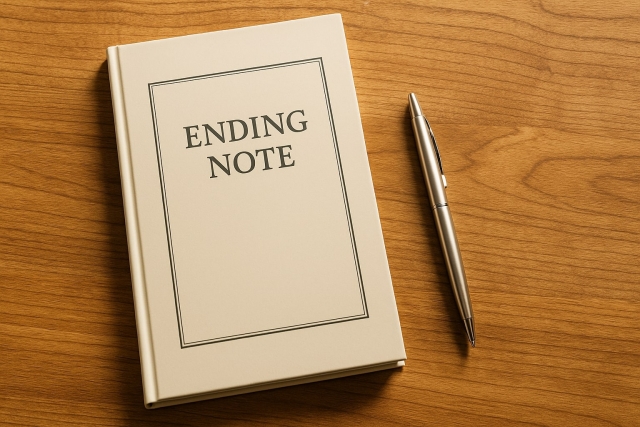相続が発生したらまず最初にすべきこと
ご家族や大切な方が亡くなられた時、様々な手続きをすることになります。相続の手続きは期限が設けられていることもあり、「何から手をつけたらいいかよくわからない」と戸惑う方も多いです。焦らずに手続きを進めるために、相続が発生したらまず何をすればよいのかを今回は時系列に沿ってまとめてご紹介します。
亡くなってから7日以内にすること
まず行うことは、主に役所への手続きと葬儀の対応になります。
死亡届の提出
亡くなった日を含めて7日以内に、市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届が受理されると、火葬許可証と埋葬許可証が交付されます。これがなければ、火葬や埋葬を行うことができません。通常、葬儀社が代行してくれることが多いのでそこまで心配することはありません。
葬儀の準備と費用の記録
葬儀の準備と並行して、後々の相続手続きのために葬式関係の費用の領収書を保管しましょう。
葬儀費用は、相続税を計算する際に「債務控除」の対象となります。葬儀関係に支出した領収書をまとめて保管し、後で確認できるようにしておきましょう。またお寺へのお布施などの領収書も保管しておきましょう。領収書がない場合はメモで控えておくとよいです。
どの支出が「債務控除」になるのかについては税理士事務所で判断してくれます。
相続の準備
遺言書の有無の確認をしておきます。亡くなった方の部屋、金庫、貸金庫などに遺言書がないか確認します。以前に比べ遺言を作成している方が増えています。自筆遺言、公正証書遺言がないかを確認します。
エンディングノートの確認
遺言は作成していないが、エンディングノートを作成している人も増えています。
故人の想いや財産に関する記載があります。エンディングノートの有無を確認しましょう。
死亡届の提出
亡くなった日を含めて7日以内に、市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届が受理されると、火葬許可証と埋葬許可証が交付されます。これがなければ、火葬や埋葬を行うことができません。通常、葬儀社が代行してくれることが多いのでそこまで心配することはありません。
葬儀の準備と費用の記録
葬儀の準備と並行して、後々の相続手続きのために葬式関係の費用の領収書を保管しましょう。
葬儀費用は、相続税を計算する際に「債務控除」の対象となります。葬儀関係に支出した領収書をまとめて保管し、後で確認できるようにしておきましょう。またお寺へのお布施などの領収書も保管しておきましょう。領収書がない場合はメモで控えておくとよいです。
どの支出が「債務控除」になるのかについては税理士事務所で判断してくれます。
相続の準備
遺言書の有無の確認をしておきます。亡くなった方の部屋、金庫、貸金庫などに遺言書がないか確認します。以前に比べ遺言を作成している方が増えています。自筆遺言、公正証書遺言がないかを確認します。
エンディングノートの確認
遺言は作成していないが、エンディングノートを作成している人も増えています。
故人の想いや財産に関する記載があります。エンディングノートの有無を確認しましょう。
死亡から14日以内にすること
亡くなった方が世帯主であった場合、年金を受給している場合は、それに関連する手続きを行う必要があります。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失届
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、保険証を返却し、資格喪失の手続きが必要です。加入していた保険の種類によって手続き先が異なります。会社員の場合はその勤め先に問い合わせます。国民健康保険の場合は市役所で手続きとなります。
世帯主の変更届
世帯主であった場合、残されたご家族の中から新しい世帯主を決める必要があります。
年金受給停止手続き
年金を受給していた場合、受給停止の手続きが必要です。また未支給年金の請求も続いて行います。この未支給年金の請求が完了した後に、年金の源泉徴収票が届くことになります。亡くなった方が確定申告をしていた場合は必ず手続きしましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失届
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、保険証を返却し、資格喪失の手続きが必要です。加入していた保険の種類によって手続き先が異なります。会社員の場合はその勤め先に問い合わせます。国民健康保険の場合は市役所で手続きとなります。
世帯主の変更届
世帯主であった場合、残されたご家族の中から新しい世帯主を決める必要があります。
年金受給停止手続き
年金を受給していた場合、受給停止の手続きが必要です。また未支給年金の請求も続いて行います。この未支給年金の請求が完了した後に、年金の源泉徴収票が届くことになります。亡くなった方が確定申告をしていた場合は必ず手続きしましょう。
いよいよ相続財産の確認へ
これらの手続きを終えたらいよいよ本格的な相続財産の確認を始めます。これは、後の「相続放棄」の判断や「相続税申告」に不可欠な作業です。
遺産の全体像を把握する「財産の確認」
まずは、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を確認します。
「プラスの財産」
預貯金、株式、不動産、生命保険などです。
通帳、証券会社の取引報告書、固定資産税の納税通知書、保険証券などで確認しましょう。
「マイナスの財産」
借入金、ローン、未払金、保証債務などです。
金融機関との契約書、請求書などで確認しましょう。
相続放棄の検討を始める
財産確認の結果、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を明らかに上回ることが判明した場合は、「相続放棄」を検討する必要があります。相続放棄の期限は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内となっています。 3ヶ月というと余裕があると思われますが、相続手続きをしているときはあっという間に過ぎていきます。特に借金が多い可能性のある場合は急いで財産を確認し、場合によっては弁護士など専門家に相談する必要があります。
遺産の全体像を把握する「財産の確認」
まずは、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を確認します。
「プラスの財産」
預貯金、株式、不動産、生命保険などです。
通帳、証券会社の取引報告書、固定資産税の納税通知書、保険証券などで確認しましょう。
「マイナスの財産」
借入金、ローン、未払金、保証債務などです。
金融機関との契約書、請求書などで確認しましょう。
相続放棄の検討を始める
財産確認の結果、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を明らかに上回ることが判明した場合は、「相続放棄」を検討する必要があります。相続放棄の期限は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内となっています。 3ヶ月というと余裕があると思われますが、相続手続きをしているときはあっという間に過ぎていきます。特に借金が多い可能性のある場合は急いで財産を確認し、場合によっては弁護士など専門家に相談する必要があります。
早めの「専門家相談」が安心感に
相続手続きは一生のうちに何度も経験するものではありませんので、専門家である税理士事務所に相談することをおすすめします。
税理士事務所に相談することで、これから何をしなければならないのか、何を検討する必要があるのかが明確になります。ある程度財産の内容がわかっているのであれば、相続税の納税の有無、相続放棄、遺産分割協議についてのアドバイスも早めに受けることができます。中でも「遺産分割協議をどのように進めればよいか」という相談は多く寄せられます。
遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合いによって決まります。概算でも財産が把握できていれば、相続人の意向をもとに分割の方法や割合、相続税の負担についても早めに確認していくことができます。
相続税の観点から見て最も有利な分割方法や、相続人の希望に沿った分割を行った場合に相続税がどのようになるのか、といった点についてもサポートを受けることができます。
税理士事務所に相談することで、これから何をしなければならないのか、何を検討する必要があるのかが明確になります。ある程度財産の内容がわかっているのであれば、相続税の納税の有無、相続放棄、遺産分割協議についてのアドバイスも早めに受けることができます。中でも「遺産分割協議をどのように進めればよいか」という相談は多く寄せられます。
遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合いによって決まります。概算でも財産が把握できていれば、相続人の意向をもとに分割の方法や割合、相続税の負担についても早めに確認していくことができます。
相続税の観点から見て最も有利な分割方法や、相続人の希望に沿った分割を行った場合に相続税がどのようになるのか、といった点についてもサポートを受けることができます。
まとめ
相続が発生したらまず何をすればよいかをまとめてご紹介しました。
木村美都子税理士事務所では、初回無料相談を随時実施しております。
「相続シミュレーション」も行っております。
どう分割すると良いかなど、様々なパターンで検討することができます。
相続税がどのくらいになるのか不安、相続税はかからなそうだけどそのまま遺産分割をしていいのか不安、相続に対する漠然とした不安等、色々あると思います。不安なこと、わからないことがある方は気軽にご相談ください。
木村美都子税理士事務所では、初回無料相談を随時実施しております。
「相続シミュレーション」も行っております。
どう分割すると良いかなど、様々なパターンで検討することができます。
相続税がどのくらいになるのか不安、相続税はかからなそうだけどそのまま遺産分割をしていいのか不安、相続に対する漠然とした不安等、色々あると思います。不安なこと、わからないことがある方は気軽にご相談ください。